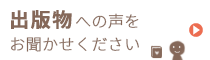- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 花の美術館
- 第20回 『熱帯植物巡礼』
- マダガスカル島
マダガスカル島
マダガスカル島はアフリカ大陸の南東約400kmにあるサツマイモの形をした世界第四の大きな島で、南北1,500km、東西約400kmある。面積は58,704km2(日本の1.5倍)で、人口は940万人である。フランスの植民地から一九六〇年六月に共和国として独立した。
マタガスカルの名の由来は、まずマルコ・ポーロがソマリア(アフリカの角といわれる地域)のモガディシュ地方のことを人伝に聞き、誤って『東方見聞録』にマディガスカルと記載したことに始まるもので、一五〇〇年にこの島を発見したポルトガル人(おそらく一四九八年、ヴァスコ・ダ・ガマ)が、誤ってマディガスカルと命名したことによると言われている。
この島は、古生代から中世代に南半球にあったゴンドワナ大陸の分裂した陸塊とされ、分裂したインド亜大陸の北上とともに広がってできたインド洋を約一億年かけて現在の位置に移動したと考えられている。隔離されて気の遠くなるような時間帯は、この島に生息する動植物に独自の進化をもたらしたのである。
植物の大半がこの島だけに分布し、700属800種以上の植物のうち、20%が固有属、80%以上が固有種で、九つの固有科が知られている。動物でも昆虫、爬虫類、鳥類などの固有種が多く、なかでもキツネザル類など原猿類の種類が多い。特徴的なのはサル、ハリモグラ、コウモリ以外の哺乳類がほとんど生息していないことである。
気候的には、インド洋に面した東海岸沿いは南東からの貿易風で、2,000mmから3,000mmの降水量があり、熱帯降雨林が発達しているが、九月から十一月は乾期で、ほとんど雨は降らない。首都タナナリーボのある中央高地は、南北に海抜900mから1,500mの高原が続き、五月から十一月が乾期、十二月から四月が雨期で、雨量は1,500mmから2,000mmとなって、灌漑による稲作が盛んである。山岳部の棚田は日本の風景とそっくりである。モザンビーク海峡に面した西海岸の北部は雨量1,000mmから1,500mm、南部は1,000mm以下のサバンナ気候で、バオバブの疎林は代表的な植生である。南部の500mm以下の内陸部には半砂漠地帯が広がり、固有のディディエレア科やパキボディウム属の植物が自生する。
十月二五日、午前十時半、首都のタナナリーボ着。予定では前日成田を出発し、モーリシャスで一泊の予定であったが、モーリシャス航空が乗り継ぎのシンガポールに来ておらず、やむを得ずシンガポール泊りとなった。当朝早く出発し、インド洋を横断して、丸一日かかってやっと着いた。日本からの時差は六時間である。
空港は市の北およそ20kmの郊外にあり、市内に向かう川沿いの道は片道一車線で、あたりには見渡す限りの田圃が広がり、遠くに小高い丘が点在している。今は乾期のためか、伸びた稲はなく、日本の冬枯れの農村風景によく似ている。田おこしにも少し早いのか、水の引いた田ではのんびり「コブ牛」が放牧されている。この時期は川床や田の粘土でレンガを作ることが盛んで、型で抜かれた生レンガを日干しにしてから積み重ねて焼き、家の建築材や垣根、道の舗装材などに利用している。
タナナリーボは、かつてメリナ族のイメリナ王朝が栄えていた。今でも丘を中心とする一帯は旧王宮やその時代の古いレンガ造りの家が並んでいる。首都名はその時代以前からあったらしく、メリナ族の言葉で「千人が集まる場所」の意味である。マダガスカルは本来無人島で、人間が住みつくようになったのは紀元一世紀前後からといわれ、多くは貿易風に乗って渡来したインドネシア系住民で、他はアラビア系、黒アフリカ系、近年になって中国系も少数いる。
町に近づくにつれて、道の両側は戦後の日本のヤミ市のようで雑多な店が軒を並べ、喧噪と異臭が漂っている。単線の鉄道線路を越えるといよいよ中心部へと入って行く。丘の麓には、上野の不忍池ぐらいのラツクアヌシ池があり、ほとりに独立記念碑、池を巡る並木はジャカランダ(Jacaranda)で、紫色の花盛り。おそらくフランス植民地時代に植えられたものであろう。樹高は20から50m、樹齢は百年ぐらいと見た。ノウゼンカズラ科ジャカランダ属は南米原生の半落葉高木で約50種がある。花期でも葉がついているものをよく見かけるが、ここは1,300mの高地で、冬は落葉する。今は春、花だけが見事に枯木を彩っている。数日後落着いてから再度写真を撮りにきたところである。バスの車内からでは気づかなかったが、小枝からしたたり落ちる水滴で傘が要るほどで、開花期の水上げの多さにびっくりしたものである。
投宿する三階建てのタナ・プラザ・ホテルは、市のメイン・ストリートの中でも駅前の角地にある。植民地時代からフランス人経営の由緒あるホテルで、外国から来る動植物調査団がよく宿泊に利用している。バスが着くやいなや、物売りや物乞いがワーッと集まり取り囲まれた。売り物は竹に彫刻をした長い筒に糸を張った現地の楽器、三葉虫の化石(島の南西部で採れる)など。物乞いは大抵が裸足の女性で乳飲児をだっこしているという、オーソドックスなスタイルである。中にはバスがホテルに着くや他人の乳飲児を借りてくるしたたかな女性もいる。東南アジアも含めて、物乞いや乞食は地域の人々とは仲が良く、職業による階級制、人種差別などもほとんどない。
歩道は広く、片道三車線の道の突き当たりはT字路で、正面がタナナリーボ駅、ホテルは向かって左角にある。立派な駅舎がある。鉄道はフランス植民地時代に敷かれたもので、単線。ディーゼル車が南に約150kmのアンツィラベ、東に約300kmのタマタブ港に週二回だけこの駅から出る。自動車の方が早いが乗車賃が安いので、屋根まで客と荷物で一杯となる。駅に平行する道路は幅12m、毎朝野菜の路上市場が両サイドに立つ。準備は三時頃から始まり、馬車や荷車で野菜が運び込まれ、市は四時頃から賑やかになり七時頃に終わりとなる。
○チンバササ動植物園
ホテルに荷を置き、午後は市内にあるチンバササ動植物園に見学に出かける。ここは日比谷公園ほどの広さである。この日は日曜日で現地の家族連れが多い。
正門から園内に入る通路は狭く、右側は池で仕切られている。池の周囲にはマダガスカルの固有種ティフォノドルム(Typhonodorum lindleyanum)の群落がある。全体にはクワズイモに似ているが、バナナ状の偽茎は高さ2mにもなり、大きな長い矢尻形の葉を含めると3mになる。これは島の東部海岸から山岳部まで、多少海水混じりの汽水域から谷川まで広く水のある場所に分布している。普段は食料として食べないが、荒歳時には水中にある巨大な芋を掘り起こして、アク抜きをして食べるという。
しかしこの国は日本から見て米を主食にする最西端の地で、米生産が228万tあり、国民一人当たりにすると240kg(四俵)になる。ほかに牛が約1,000万頭、キャッサバ181万t、サトウキビ153万t、バナナ28万t、コーヒー豆8万t、ヤギ150万頭などを生産し、自給率は常に100%以上で飢えることはない。
公園には自然林も残され、高木類はタマリンド、カリアンドラ、人工的にはアラウカリアなどだが、日本のヤチダモ(トネリコ属植物)に似た高木が、総状に翼果をたわわに垂らせている。それも一、二本でなく、数十本の単位である。
モクセイ科トネリコ属は北半球の温帯に約70種、日本に9種あり、アメリカ、ヨーロッパ、北アフリカ、インド、中国などに分布しているが、南半球のマダガスカルにあると記載している図書はない。琉球列島からインドまで分布するシマトネリコ(Fraxinus griffithii)は観葉植物として日本で利用されている常緑樹だ。元祖トネリコ(F. japonica)は本州中部以北に分布する落葉高木でよく田の畦道の並木として植えられ、竹や丸太を渡して刈り取られた稲束を干す木(稲架)として使われる。秋の北陸や越後路の風物詩として有名であるが、最近では天然乾燥が減り、トネリコの並木は耕地整理とともに伐採され、その田園風景は激減している。アオダモやヤチダモなどの仲間は材の反発係数が高く、昔から運動用具として、野球のバット、肋木、平行棒、平均台などに利用されている。
池の中央には島があり、ワオキツネザルなどの原猿類が見せ物のために飼育されている。池の辺りに広がる芝生に六人連れの家族がシートを敷いて輪になって弁当を楽しんでいて、その傍らに、高さ10m以上のタコノキの仲間がたくさんの気根を垂らし鎮座していた。これは島の固有種Pandanus princepsで、三角錐の樹形が優雅なことからプリンケプス(最も気品のある、の意)の種小名がつけられたもので、一見すると針葉樹のように見える。この島はもともと針葉樹はなく、マツ類、ヒノキ類はすべて人為的に持ち込まれたものである。マダガスカルにはタコノキ属の種類が多く、川辺、海辺は無論のこと、乾燥地の岩場に自生するものもある。パンダヌス・プリンケプスは中西部の内陸部まで分布し、乾燥地の川筋に多く自生している。
ヤマドリヤシ(Chrysalidocarpus lutescens)の大株があり、これもこの島の固有種である。ほかにトックリヤシ、トックリヤシモドキ、ミエミツヤシ、ハナキリン、パキポディウム、ドラセナ・コンシンナ、マダガスカルジャスミン、ニチニチソウ、タビビトノキ、カランコエ類、ミドリノタイコ(ウリ科多肉植物)、多肉ユーフォルビアなど多くの種類が植えられていた。
公園の丘陵地帯は各地から集めた固有種が植えられ、一巡できるようになっている。珍しいところでは、ブドウ科の壺形植物で地下から地上部に突き出た巨大な塊根をもつものがあった。乾燥地に耐えるべく水分貯蔵組織が発達したもので、植物のしたたかな適応変化である。壺形植物の代表選手といえば、ワサビノキ、パキポディウム、バオバブだが、ここに植えられているものは若木であまりその特徴が出ていない。尤もバオバブの成木は重さ100t以上あり、超大型のトレーラーでもなければ運搬は不可能である。
ディディエレアやミドリサンゴ、カランコエなどの間にジンチョウゲ科ガンピと見られる低木がオレンジの散形花序の花をつけている。湯浅浩史著『マダガスカル異端植物紀行』によると、やはりこの皮を漉いて和紙に似た紙が作られているとのことである。この植物園にはハナキリンのコレクションが多く、大形から小形、花色も白、黄、オレンジ、緋、赤などのバリエーションがある。
○麻の話
丘の中腹にリュウゼツラン科の大形植物が数株目についた。サイザル(Agave sisalana)である。サイザルはメキシコなど中米が原生地で、かってメキシコが大規模に生産し、その繊維がロープや麻布に加工され、ユカタン半島のつけ根にあるシサル(Sisal)港より輸出されたので、サイザル麻の名がある。現在のメキシコでは、自国で使うコーヒーの豆袋、カカオの実を入れる袋やロープなどを自給できる程度の生産である。これは乾燥した荒地でもよく育つことから、産地はアフリカやインド洋の島々へと移っている。マダガスカルでは南部の乾燥地を中心に年間2万tの生産がある。
麻といっても繊維としては色々あり、元祖の麻(Cannabis sativa)は大麻とも呼ばれ、中央アジアが原生地である。アサ科の一年草で、日本には弥生時代に渡来し栽培が始まった。皮は繊維として利用するほかに、花穂や葉に幻覚物質があり、麻畑で働く人々に麻酔いがあるという。古くは、「苧」と呼ばれ、皮を剥いで漂白したものを「苧殻」と呼び、盆の迎え火、送り火を炊くのに用いられている。昔忍者がジャンプ力をつけるために毎月何千回となく跳び、最終的に草丈の2.5m以上を飛び越えることができるようになったと言われるくらい麻の成長は早い。
麻はアサでもマニラ麻(Musa textilis)は高さ4mになるバナナの仲間で、原生地のフィリピン、東南アジア各地で生産している。葉鞘から弾力がある強い繊維がとれ、比重が小さく、耐水性に優れていることから、船舶用のロープに使われるほか、敷物や漁網などに利用されている。最近はいずれも化学繊維に押され、生産は減少しているが、別の使い道、つまりパルプ原料として注目され、製紙用に需要が増えつつある。
ほかに麻のつく繊維植物にチョマ(苧麻)がある。イラクサ科ヤブマオ属の一種Boehmeria niveaで熱帯アジアが原生地だが、日本にも野生化している。白チョマ、緑チョマがあり、白が上質。ロープ、網の他、消火ホース、蚊帳などを作り、ブラジルではコーヒー豆を入れる袋を作る。日本では手をかけて灰汁につけ水洗いし、雪上で晒す、などしたものは布に織られ、上布と呼ばれ、越後上布、小千谷縮、宮古上布などが昔から有名。布を織って晒したのが縮、晒した糸で織ったものが上布である。
ジュート(Corchorus capsularis)は黄麻とも呼ばれ、シナノキ科の草本でインドから中国の熱帯が原生地といわれ、栽培の多いのはインド、バングラデシュ、中国、タイの順であるが、最近はブラジルでの栽培が多くなっている。播種後百日から二百日で収穫し、茎から皮の繊維をとる。ほかの麻ほど丈夫でないが、安価のため、ほとんどが麻衣(南京袋)として利用される。最近はモロヘイヤと称し、日本でも夏のころに健康野菜として売られる。少しヌメリや泥臭さがあるが、強壮作用があるといわれている。
桐麻といわれるイチビ(Abutilon avicennae)はインド原生のアオイ科の一年草で、茎を水浸し発酵させてから表皮の下の繊維をとるが、粗くてもろく、ほとんど単独では用いず、ジュートに30%位混ぜてロープや麻袋をつくる。日本には古い時代に入ってきたが、近年では栽培されず、野生化している。まあ麻といっても色々あり、ご多分に漏れず手間のかかるものは段々とすたれて行く。
正門の左奥に二階建ての小博物館があり、民芸品や農具、三葉虫などの化石、原猿類の骨格標本など大きく二つのコーナーに分かれている。ここで注目されるのは、約四百年前に絶滅した体高2.5mはあるエピオルニスの骨格標本で、かたわらに破片を集めて復元された長さ30cmの卵が展示してある。ダチョウに似て飛べないこの鳥は、ヨーロッパには象を食べる鳥(島には象はいない)と誇張されて伝えられ、ダ・ヴィンチの絵画にも描かれている。また『アラビアン・ナイト』に出てくる巨大鳥ロックはこの鳥をモデルにしたといわれている。大航海時代は特に船員の新鮮な肉として乱獲され、一挙に滅んでしまったのである。同様にマダガスカルから東に600kmに点在するマスカリーン諸島(モーリシャス)には20kgを超える世界最大の飛べない鳩ドードー(DoDo)が生息していたが、十七世紀人間によって絶滅している。
ポルトガルの航海者ヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)がアフリカの南端、喜望峰を廻航して、一四九八年インドの西岸カリカット(コジコーテ)に到着したのは、今からほぼ五百年前である。彼はその途中マダガスカル西海岸のトリアリーに寄港したといわれ、この時代まだエピオルニスは生息していたので、彼らの格好の鳥料理にされたと思われる。この鳥は南部に多く生息し、今でもトリアリー(トゥレアール)郊外の砂丘から卵の破片が出土する。ここに展示されている標本は全部が本物で、レプリカを作ろうにも技術がなく、外注したのでは高くつき、結局は本物復元が一番安価とのことである。
館を出ると花壇に高さ20m近いジョオウヤシと見られるヤシが数本かたまって植えられ、標示板にはシアグルス(Syagrus romanzoffiana)とある。シアグルスと言えばわれわれの間では八丈島で生産されているブラジルヒメヤシ(S. weddelliana)がポピュラーであるが、この属は南米に58種あり、20mを超す高木も多い。帰国後よく調べたらジョオウヤシをシアグルス属に分類する見解もあるとのことだった。ジョオウヤシの見立てはそのものズバリ当たっていた。
○無事故の双発機
十月二十六日、MD八六一便で、午前八時四十五分タナナリーボ発。西部の海岸都市モロンダヴァに向かう。
双発十五人乗りの飛行機はほかの乗客の乗り合わせで、われわれは二班に分かれた。飛行機は一機でピストン輸送となった。距離は首都から南西に約四400km、プロペラ機では一時間半の飛行である。老年期の中央山地の山々は、標高900から1,500m、女性的ななだらかな様相を呈し、赤褐色、裸の大地のわずかな窪みが細く入り組んで濃緑色の植物の存在が認められ、4,000mの上空から全体を見ると、あたかも多くの皺を持った人間の脳のようにも見える。複雑な溝が集まって、やがて赤濁したツィリビヒナ川と成長してモザンビーク海峡に注いでいる。モロンダヴァは人口五万人ほどの地方都市であり、年平均気温24℃、降水量は300から500mm、周辺の乾燥した山地にかけて、キワタ科のバオバブが自生する地として有名である。特に150kmの北にあるベマラハ自然保護区はユネスコの世界遺産にも登録されている。最近は世界遺産登録のラッシュである。これに登録すれば観光客が多くなるメリットも考え、金も使って無理矢理登録したのではないかと疑わしいものまである。地球の大自然が創造したものは本物の遺産、いや財産の方が適切である。遺産は死んだ者が残した財産で、財産は時空を超えた宝である。さて飛行機は着陸態勢に入ったため、少しずつ高度を下げ始めるころ、巨大なバオバブが地面にマチ針を刺したように散在し、肉眼でもある程度単位面積の植生数が分かるようになった。このあたりの乾燥が強い場所では、1km2当たり50から100本程度で、水分の多い池や川などの付近では倍以上の密度である。またザー・バオバブのようにかたまって数百本の純林を作るものもある。飛行機はエンジンの回転を下げ、滑走路を目指す。この小型機は今までに事故を起したことがないとのことである。その無事故の原因はパイロットが整備士を兼ねて管理しているとかで、自分が乗るものに手落ちがあったら命取りになるわけで、必然的に整備も完璧にやるかららしい。何でも分業でやっている高度文明国では、飛行機に限らずまた意図的であるなしにかかわらず手違い、手落ちが毎日のニュースとなって出てくる。病院での患者の取り違いで手術や輸血ミスなど日常茶飯事であまりに続くので事件としての新鮮さもなく、ニュースを聞く方も脳がマヒしてあたりまえの感覚になって、異常が異常に感じられないのは本当の異常である。
着陸してびっくり、飛行場は塀や鉄条網も満足に張られていないローカル空港で、場内ではニワトリの親子が群をなして餌を拾っている。ヒナの中に一匹だけ、アヒルのヒナが混じって、尻をふりふりガーガー鳴きながらついて行く様子に飛行中の緊張がほぐれ、小さな歓迎パレードに微笑がもれた。空港建物は一階建てで、現在出発ロビーを増築中である。飛行機はわれわれを下ろしてから給油して、再び二班の連中を迎えに反転。この日は大忙しのようだ。
この日のホテルは海に面したブーガン・ヴィリエである。これはフランス植民地時代からのコテージ式ホテルである。面積は約1,000坪、二人部屋のコテージが十数戸あり、日陰樹にはココヤシ、タマリンド、アオイ科のハマボウの一種など、生垣や隣との仕切り植栽にはコダチアサガオ、ハイビスカス、ブーゲンビレアなどが混植されている。マンゴー、トゲバンレイシがたわわに実を成らせている。トゲバンレイシ(シャシャップ)は海岸で風抜けがよいのにもかかわらず、カイガラムシが付着し、排泄物でスス病になっているものが多く、到底もいで食べる気になれない。
○マングローブガニとヤシガニ
第二班が到着するのは二時頃、その間第一班のわれわれは、海峡から吹いてくる心地よい風と遠く近く白い帆を張った帆引き漁船を借景に、オープンレストランでビールで乾杯。昼食のメイン・ディッシュは茹でたマングローブガニ(Scylla serrata)である。ノコギリガザミの和名があるようにガザミの一種で、英名はマングローブ・クラブという。生きているうちは真黒で、主にマングローブの泥土などに穴を掘って生活している。2~3kgになるごっついカニでハサミの力は強く、下手に鋏まれると指を切り落とされる。卵から孵化した幼生(ゾエア)は海流に集まり伝播し、全世界の熱帯地域に広く分布している。
日本では八重山列島に生息しており、西表島の民宿では今でも予約しておけば食べることができるが、乱獲で年々小型化しているとのことである。この島はヤシガニも多く、七、八年前に訪島した時も、この夜行性のカニを捕獲しに行ったことがあった。日のとっぷり暮れた海岸の岩場の穴がかれらの住拠である。同時にそのような場所はサキシマスジオというアオダイショウに似た大型のヘビも住んでおり、懐中電灯に小さく反射するものはすべてヘビである。その多さにたじろぎながらそれでも四匹ほどヤシガニを獲え、料理は翌日とばかり空の風呂桶に監禁したが、そのうるさいこと、夜中大騒ぎであった。翌日に釜茄での刑となったわけだが、「このヤシガニは死んだイノシシや山猫、毒を持ったハブなどを食べているので、本体は食べられない。ハサミだけにしておいた方がよい」とのことで、全員十五名の均等割では、なめるほどしか配給されなかった。話では毒気を持ったヤシガニは、茄でると紫色になるとかで、古老の話は経験からの結論であり、従った方が無難である。
ヤシガニは名前がカニだが、ヤドカリの仲間で一属一種(Birgus latro)である。書物では昔から八重山列島では中毒が発生しており、症状は食後数時間で発症し、下痢、嘔吐、悪寒、倦怠感、関節痛などで体力を消耗し、回復まで数日間寝込むケースが多く、重症の時は死亡する。
ミクロネシアやポリネシアでもヤシガニ中毒は発生しており、原因は食物連鎖によって、外部から取り入れられるものである。沖縄ではリュウキュウガキやハスノハギリ、クワズイモなどの複合による毒といわれており、やはり食べるには二、三日絶食させてから調理するとよいという。ハサミの肉や腹部は脂が乗って美味である。ヤシガニは甲長12cm、体重は1から3kgになる。日本人の物珍しさからマリアナ諸島では、一匹5,000から7,000円で料理として出されるが、南洋、東南アジアではなんといっても、前者のマングローブガニが一番で中華料理としても人気がある。
午後二時。第二班到着。大きな荷物は今回基地とするタナ・プラザ・ホテルに置き、全員がカメラ、着替えの下着だけといった軽装備で、共通して持っているのが蚊取線香である。
マダガスカルにはまだマラリアがある。特に北部のマシベ周辺に訪れる際には、メフロキンなどの予防薬の服用が必要となる。蚊取線香はジョチュウギク(Pyrethrum cinerariifolium)から作られ、成分は主に子房に含まれているピレトリンである。この成分は変温動物の神経系統を麻痺させる働きがあり、鳥や人間などの恒温動物には無害である。原生地はバルカン半島で、日本では一八八七年から栽培が始まり、戦前は世界一の生産国で九割が輸出されていた。日本での主産地は瀬戸内海沿岸だった。現在は化学合成されたアレスリンに替わっているが、生産国はアフリカのケニアが第一で、ほとんどが輸入物である。しかも薬効目的でなく、線香の材料と香り付けを加える役目だけになっている。蚊取線香は日本の発明で、外国では粉末をそのまま用い犬、馬、猫、小鳥などのノミ、シラミの駆除剤とされてきた。戦後、日本に進駐した米軍はジョチュウギクを燃やすなど何とナンセンスで、不経済なことをやっていると笑ったそうだが、後で調べてみると燃焼という高温で有効成分のピレトリンが何十倍も増加することが解かり、日本人の知恵に感心したそうだ。線香は花・茎・葉の粉末に松葉と緑色染料を加えたもので、最近では電気蚊取も普及しているが、何といっても日本の夏の風物詩、ブタさんの容器とともに、俳句の季語にもなっている。
かつて八重山列島はマラリア汚染地区であり、琉球王朝時代には流刑の島であった。
昭和二十年、米軍の占領によって空からDDT、BHCが大規模に散布され、マラリア蚊は絶滅した。以来、日本でマラリアはなくなったと思いきや、南方戦線から復員した兵士の中には罹病した者も多く、三日熱、五日熱など周期的に高熱が襲い、マラリアの話を聞かなくなるのは昭和も三十年代に入ってからであった。
○バオバブの話
午後二時四十五分になり、さて、これからがこの旅の一番の目標のバオバブ観察である。二台の八人乗りワゴン車に分乗し、バオバブの聖地を目指す。モロンダヴァの町では、バオバブの姿は見当たらない。水田や雑地、放牧地が続く街道の右側に忽然と現れた森と見たのは間違いで、面積約500坪ばかりの樹の塊まりのブッシュからグリーンの傘を広げている30mの高木、正しくバオバブ(Adansonia grandidieri)である。車を降り水田の畦道、ブッシュを通ると夢にまで見たバオバブがあった。この辺では最大のバオバブで直径3.7m、幹を見上げるとまるで崖の下に立たされているようだ。あまりにも人間が小さく感じ、硬そうな幹肌に触れると、生き物の温かさを感じた。この部落の人々は聖なるバオバブを敬い、崇拝してきた。根元近くには、自然の蔓や枝で作られた簡単な祭壇があり、人々の信仰がうかがえる。神々(自然)との共存、人間が有史以前より現在まで守ってきた生き方の原点である。高度文明社会では、最も身近な親族への断絶、殺人、家庭崩壊など、文明、文化の恥部が露骨に報道される。これは自然破壊の上に成り立つ文明国の自然教育の貧困による結果である。
バオバブの年齢は巨大なものは2,000年とも5,000年ともいわれているが、年輪がなく、大きさから判断するしかない。しかしマダガスカルの植生分布は海岸から沼地、乾燥地など、範囲が広く、やはり水分の補給が充分な地域では成長が早いと思われる。マダガスカルで最大のものは、マジュンガにある直径7.4mの個体であるが、アフリカには直径10m、何と目通り30m以上というものがある。北に向かう街道から左折した未舗装の凸凹道、土埃り、いよいよここが有名なバオバブ街道である。水田や沼の辺り、またはブッシュから天地を逆さにして立っているようなバオバブが散在する。すべてがアダンソニア・グランディディエリで、この聖なる樹は葉を茂らせていたが、この辺りは未だ展葉しておらず、採り残された果実がよく見える。果実は直径12cmほどの卵形で、外皮はコールテン状の褐色の細毛に覆われている。厚さ3mmの殻を割ると、中には発泡スチロール状の白い物体が詰まっており、径8mmくらいの黒い種子がある。種子から油が採れ、フワフワしたスチロール状の果肉はラムネの味がして、そのままでも食べられるが、水に溶かして飲料として利用されるため一般の市場で売られ、貴重な現金収入源となっている。したがってほとんどが採集されてしまうため、自然実生発芽は少なく、次代の若木は探しても先ずは見つからない。
ここは道の両サイドにバオバブが20から30株規則的に並び、バオバブの並木道として、グラビア誌や植物図書によく紹介されている場所である。ちょうどこの地方は用水から水を引き、田植えが終った時期で早苗をそよぐ風が心地よい。ブッシュを切り開き、丈の低い掘立小屋が数軒あり、放飼いのニワトリが十数羽群を作って藪をあさっている。小屋の壁や天井といっても、外界とは一枚で仕切られている単純構造である。一応は切妻型だが、屋根の勾配はゆるやかである。年間300mm程度の雨は十分しのげる。尤も雨は平均的に降るわけでなく、一年のうち10日位の間に全部降り、他の350日以上はカラカラ天気というわけである。その屋根や壁の建材はバオバブの皮を剥いで乾燥させたもので、一枚が1m2から5m2位あり、用途に応じた大きさに切り取って使っている。自然素材はホルムアルデヒドやトリクロロエチレンなどの有害物質の心配はない。樹皮を切り取られたバオバブは枯れることはなく、何年かすると復元する。そういえば、ここらの木の根元から手が届く高さまで残る四角の紋様は剥ぎ取られた跡なのである。
○星の王子様(サン・テグジュペリ)
「大人はだれでも初めは子供だった、しかし、そのことを忘れずにいる大人はいくらもいない。」『星の王子さま』の冒頭に書かれている一節である。また王子に向かって、キツネは「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えない。かんじんなものは、目に見えないんだよ」……。フランス語の書物の中で最も多くの言語に訳され、世界八十ヶ国以上に出版された。もちろん作家の名はサン・テグジュペリである。小説の中で、サハラ砂漠に不時着したパイロットは子供に出会い、純真さを星の王子に託した。その星を困らせるおそろしい種子を成らせる木として、天地が逆になったバオバブが登場し、一躍バオバブという樹が世界中に知れわたったのである。
一九四四年七月三十一日、パイロットでもあったサン・テグジュペリはコルシカ島を飛び立ち、海を越え、占領下にある故国の上空を飛び、任務を終えての帰路に行方不明となった。ドイツの戦闘機にやられたとか。しかしドイツ側にはその記録はなく、一九九二年と一九九三年に、墜落したと思われる海域が捜索されたが、何の手掛かりもなかった。一九九八年九月、南仏のマルセイユ沖で漁師の網に彼の物と見られるイニシャル入りの腕輪や飛行機の残骸が引っかかった。本物のようで、引き続き捜索作業が行なわれている。星の王子さまはヒツジを連れて六年間も帰ってこなかった。しかし大戦に消えたサン・テグジュペリは五十四年後に劇的な形で帰ってきたのである。
マダガスカルでは、八種のバオバブがあるといわれ、ほかにアフリカに一種ある。幹周りの最大なAdansonia digitataは、樹高が12mになり、マダガスカルにあるが、どうも人為的にアフリカから渡来したものらしい。オーストラリアには高さ20mになるA. gregoriiがある。バオバブ街道をさらに進むと形態の変わったバオバブがある。根元が徳利状に肥大し、各枝が少々下を向いているザー・バオバブ(A. za)と、やたら枝が暴れているフニィ・バオバブ(A. fony)である。フニィ・バオバブはこの土地でも名物になっている、二本の幹がよじれて成長している巨木を見る。この辺はさらに乾燥地で新芽を吹く様子もない。バオバブは乾期が続いている時期、つまり一年の大半は落葉して、緑を茂らすのは極く短期間なのである。
短気は損気、よくまあこの巨体を維持することができるのか不思議に思う方もいるだろうが、心配無用。樹皮の下に葉緑素をもち、幹や枝からも光合成を行なっているのである。人家近くのバオバブでは、幹にオデキの跡のような丸い斑紋が規則的に上部の枝部までついているのを目にすることができる。これは果実を採るために幹に棒杭を打ち込み、人間が登る足掛かりの跡で、打ち込んだ杭が腐ると跡が残るというわけである。藪の中に赤紫の花をつけている蔓性植物がある。この島を故郷とするマダガスカルシソケイ(Cryptostegia madagascariensis)である。図鑑によれば、原生地は熱帯降雨林とあるが、後日行く降雨林には見当たらず、こんな厳しい乾燥地にあった。この植物は広く熱帯のリゾート地の庭園樹として植えられ、そのような場所では、葉は厚く、緑も濃く、光沢があり、花も大きく立派になる。しかしここにあるのは蔓も細く、葉はまばらで黄ばんで、一見別の植物のようである。栄養や環境もよい場所で肥満化したものと、悪環境でみすぼらしく見えるが、必死になって生きている姿と比べると、生物としてどちらが美しいのだろうか。
時間はそろそろ午後六時となり、並木道に戻り、日没をバックにバオバブのシルエットの撮影準備にとりかかった。夕暮時は全世界共通だろうか、カラスの動きが鳴き声とともに静まり行く一日の終焉を告げる。ここのカラスは餌の豊富な日本の大都市のように大群でなく、せいぜい二、三羽で、多くはペアである。少々小ぶりだが、黒地に首の周りが白くまるでカラーをつけたようなおしゃれなカラスである。鳴き声は日本のものよりトーンが高く、節間が短い。みんなもカメラ撮影は終ったようだ。
十月二十八日、タナナリーボから東へ250km離れたペリネ自然保護区に行く。ここはインド洋からくる湿った季節風によって、年間3,000mm以上の雨量があり、熱帯降雨林が形成されている。保護区に向かう道は単線狭軌の鉄道線路に沿って、東海岸のタマタブまで行く。港からの物資が首都に流れる大動脈、踏切も何ヶ所かあるが、事故は皆無だそうだ。
もっとも列車は一週間に一度しか通らないのと、この山間部では時速20から30kmのスピードなので、よほど間の悪さでもなければ、衝突の事故などはありえない。といっても道は舗装されているが狭く、大型車のすれ違いには肝を冷やす場面もしばしばである。全般にカーブの多い山道ばかりで、材木を載せたトレーラーが横倒しになっていたり、加えて牛や山羊の群が占領したりのアクシデントである。いやこれはアクシデントでなく、普通のできごとなのである。
山の緑は全部がユーカリ。薪炭用として植えられたもので、道々は薪炭を売る農家が多い。かつて日本の雑木林のコナラやクヌギのように根元を残せば、何度でもひこばえで再生するというわけである。
途中で「Peyriera」ファームを見学する。ここは島の各地から集められたカメレオン、ヤモリ、カエルなどが飼育されている観光農園で、中には体長60cmの世界最大のカメレオン、パースンカメレオンや2-3cmで最小のもの、体長20cmでこの国最大の蛾マダガスカルオナガヤママユ、ハリモグラなども観光の目玉である(ちなみに日本にいるヨナクニサンは体長20cm以上で世界最大の蛾である)。
保護区内にあるアナラザオトラの森は入山するのに入山料が必要で、届出とガイドをつけることが義務づけられる。低湿部には木生シダが繁り、雨量の多さを感じたが、山に入ると乾期のため何ヶ月も雨なしで、大地はパサパサ、樹木は雨がくるまで、じっと耐えている様子であった。
ブッシュ状に高さ1、2mのノボタン科の植物が径1cmばかりのピンク四弁の花を咲かせていた。ノボタンにしては厚手の葉をつけていた(帰国後、市場で同種と見られる鉢花が、コザクラノボタンと銘打って売り出されているのには驚いた。手の早いプラントハンターもいたものである)。テーブルヤシに似た小形のヤシがある。高木は何科の植物であろうか。ガイドはそこに棲む原猿類の説明ばかりで、まったく植物の説明はしない。その中でも目を引いたのは高さ7-8mの枝先からシルク色したボーリングのピン状の繭で、説明によれば先程のマダガスカルオナガヤママユらしい。あまりの巨大さに二十個ほど集めれば、絹織物の一反ぐらい紡げるかもしれない。いずれにしろ稀少、貴重、紬は相当に高価になるだろう。
林縁はこれもオーストラリアと陸続きだった証か。グレビレア(羽衣の木)が、特徴ある多数の雄しべで飾られた白い花を咲かせていた。びっくりしたのは、チャ(Camellia sinensis)の原生林のような群落があったことで、中には白斑の入ったものも確認できた。チャは無論中国南部が原生地、昔誰かによって持ち込まれたものが、自然増殖したものであろう。ちなみにこの国でも茶を飲む習慣があり、スーパーストアなどで茶を売っている。とにかく安く、物は試しと買って飲んでみた。ただ摘んだ茶を乾燥させたもので、煮出して飲むのだが、味も塩気もない代物。やはり日本茶に限る。
十月二十九日。南部の町フォルト・ドーファンへ行った。首都から約300人乗りのジェット機で三時間十五分。宿泊ホテルのドーファン・ホテルに大きな荷物を預け、とりあえず岬のレストラン「ミラマール」でシーフードの昼食をとった。実をいうと、この国にきてやっと好物の貝料理や魚の料理にありつけたわけで大満足。庭に一本アルアウディア(Alluaudia procera)が植えられ、特徴のある刺だらけの幹が天を突いて、いよいよこの島の固有科ディディエレア科(Didiereaceae)の自生する地に入った感がある。同科は四属十一種があり、鋭い刺と一緒にまだ刺に変形していない小さな葉を持つことは、サボテンより進化しておらず原始的であるといわれている。彼らの生息本拠地は年間雨量500mm以下の内陸部で、この辺りに見かけるものは人為的に植えられたものである。昼食後は町の水源の湖に向かう。この湖は海に近く、湖というより潟というべきで、岸辺にはマダガスカルのクワズイモともいうべきティフォノドルムの群落。そしてもう一種、ここだけの固有種のパンダヌス(Pandanus dauphinensis)が混生している。高さ3mの幹の先端に盃状に広げた剣葉は一見してユッカの仲間に見える。
フォルト・ドーファンの町は、外洋から大きく入り込んだ湾の最奥部にあり、小さな港はあまり活用されていないようで、施設やコンテナも赤錆びて放置されている。湾内には廃船が打ち上げられ、煙突とブリッジだけが海上に出ている沈没船もある。湾を取りまく山々は標高500から600mで、海に面して切り立った崖は中生代のジュラ紀(一億八千万年前)にゴンドワナ大陸が分裂してアフリカ、インド、オーストラリア、南極大陸などに分かれた時の跡で、その形は遙か5,000km以上離れたオーストラリアの西海岸の崖と合致するという。
日本では、初夏の香り鉢花として人気のあるマダガスカルジャスミンは、この辺の海岸が原生地で、塩にはめっぽう強く、太平洋、インド洋の海浜リゾート地に多く植栽されている。名前はジャスミンでもモクセイ科ソケイ属でなく、ガガイモ科の植物で、本当の和名はマダガスカルシタキソウ(Stephanotis floribunda)である。元祖シタキソウは千葉県から九州の海岸林に生える蔓性植物で、花は白色、これにも芳香がある。園芸名に使われるジャスミンは、香りの良い花につけられる形容語として使われることが多い。
○サイアディ公園
午後の植物探査は、郊外にあるサイアディ公園に向かう。道すがら小さな村で果実を売っている。世界最大のジャツクフルーツである。これは生食できる部分は種子の周りのわずかな果肉だけで、通常はブツ切りで香料や砂糖を加えて煮て食べるものである。直径12cmの心臓形をしている果実はギュウシンリ(牛心梨、Annona reticulata)で、大きいものは1kgあり、広く熱帯で栽培され、中米が原生地のバンレイシ科の植物である。本によるとバンレイシ(シャカトウ)に劣るとの記述が多いが、ここのは味も糖度もバンレイシに勝るとも劣らない逸品である。
道路の両側は畑や田に利用されているが、自然のブッシュが残され、高さ7-8mのカリステモン(Callistemon)の純林が目につく。なかにフトモモ(Syzygium jambos)など、多少の混生も見られる。ブラシノキ、キンポウジュの名でも知られるが、カリステモン属はオーストラリアの固有属で、約三十種があると書かれている。ただしマダガスカルにあるとは書かれていない。小枝の周囲に虫の卵のような木化した蒴果がついているのを見ると確かにカリステモンである。
こんな田舎に、わざわざオーストラリアの木を植える者も居るはずがなく、おそらく自生種であろう。バオバブと同様に大陸分裂の生き証人かもしれない。サイアディ公園は土埃のたつ街道沿いにあり、ワニやキツネザルも飼われ、付近から集められたタビビトノキ、テリハグァバなどが植栽されている。見ごろなのは世界最大の羽状葉を持つラフイアヤシの一種(Raphia ruffia)で、それが堀で仕切られた小島に植えられて、前述のワオキツネザルが放たれている。ラファイアヤシはマダガスカル、マスカリーン諸島、アフリカに三十八種があり、熱帯アメリカに一種あるといわれている。本種はその中の最大で直径2m、高さ10mになり、葉は長さ15から18m、果実は鶏卵大でアルマジロのような鱗片で覆われている。果肉は食用にされ、巨大な葉は敷物や織物などに利用されている。公園の奥はなだらかな丘陵地帯になっており、所々に珪岩が露出している場所がある。そこにはパキボディウムの小形低性種数種の自生が見られる。
ほかにカランコエやベンケイソウなど、わずかな一枚岩上に固有各種が見られ、あたかもサンプルの展示場のようである。
○乾燥林を目指す
十月三十日。町の西方90kmにあるベレンティ動植物保護区へ行く。ここは年間雨量350mm(東京の四分の一)の乾燥地で、一九三九年にこの地にサイザル麻のプランテーションで成功したフランス人、アンリ・ド・オルム氏が設立した私設の保護区があり、現在でもそのファミリーによって維持されている。ここは完全に隔離されている地域で宿泊客かサイザル畑の作業員しか出入りできない。午前九時に、町のホテルのル・ドーファンを出発した。平野部はちょうど田植えの最中であった。街道沿いに広がる田園風景はアジアの臭いがする。こんもり繁った低地帯が見えてきた。ここにはネペンテス(Nepenthes madagascariensis)が自生している。ネペンテスはボルネオを中心として東南アジア、太平洋諸島に分布しているもので、ここが分布の西の限界となっているのである。筒形の捕虫袋の底に溜まっている液は昆虫などを溶かす消化液で、二日酔いとか胃の調子の悪い時に飲んでも効果があるという。コシダを覆うようにはびこる群落はかなりの量である。道路の反対側は少し小高い丘になって疎林になっており、林床にワラビが群生している。まだ展葉前のものを摘み取りビニールに包み、内緒で日本に帰ってから湯掻いてオヒタシで食べたが美味かった。ワラビは温帯から熱帯まで湿潤地なら世界中にあるが、野菜としてまた、加工してワラビモチなどとして食べるのは日本人位なものである。
凸凹道を行くこと一時間半。ようやく山間部となる。ウツラウツラしていると突然、「ガァー」という大音響にびっくり!鉄橋を渡る時の音で、橋の骨格と車が乗る渡し鉄板(U字連続板)が完全に固定されておらず、車が通るとこんな音がするわけである。7、8m下の河の水は濁っているが、数人の女性が洗濯に余念がない。子供達は水遊び、男達は網で魚を追っている。このあたりはアンタヌシ族の村。彼らの墓は高さ3mくらいの先の尖った四角錐で、数十基並んでいる様は壮観である。この村でもギュウシンリを露店で販売しており、員数だけ買うことにする。村のはずれに、五歳から十歳くらいの子供達が道路の穴を埋め戻す工事をやっている。徐行して通るとみな、車に向かってごほうびを要求する。ガイドのセルジュはそれを無視して車を進めた。話を聞くと「あれは小遣いかせぎで、埋め戻しはインチキで道路に土を盛っただけ」だそうで、毎日通る車にせびるのが日課とのことである。まあ植物もしたたかに生きているが、人間も子供のころよりしたたかである。
広い谷間を縫うように道路が通り、坂もいくぶん急になるころ、アンタンドロイ族とみられる村がある。道畔のホウオウボクが緋色の花を満開に咲かせ、あまりの見事さに車を止めて写真撮影していると、すぐ子供達が集まる。ポラロイドカメラで撮るものがおり、写真二枚を子供に与えたところ、それを巡って写真の争奪戦となり村は大騒ぎである。この辺では自分の写真などは、一生で二、三回しか撮ることはなく、写真は貴重な宝なのである。騒ぎの村を後に山道を行く。
マダガスカルの山はすべてが老年期の山で、長年の風化によって急峻なものはなくなり、なだらかである。谷の反対側の斜面にタビビトノキの大群落があった。オウギバショウとも呼ばれ、葉が規則正しく二並列に開張し、東西に広がり方向がわかる羅針木といわれているが、原生地を見る限り、各々バラバラでこの説は当てはまらない。羅針木として有名なものはアフリカはナミビアの高原にあるヒカリドウ(光堂)という園芸名をもつパキボディウム(Pachypodium namaquanum)で、茎の上部がみな、北に向かって30度傾くので正確に方向が解かるといわれている。さて旅人木のいわれだが、葉鞘に溜まった雨水を渇いた旅人が飲んだからだという説があるが、定かでない。
ラベナラ(旅人木)は水辺から乾燥地(年間500mm)まで分布の範囲も広く、自生地では全体を建材用として利用するために、それぞれ採集の権利が決まっている。谷を登り切り、最後の橋を渡ると大きく開けた高原が現われ、風景は一転して、当地に固有なディディエレア科(Didiereaceae)と多肉ユーフォルビアの疎林となり、その林から点々と頭を出しているものがある。これはバオバブモドキといわれるワサビノキの一種(Moringa drouhardii)で、一見バオバブを小形にしたような樹形である。ワサビノキ科はワサビノキ属のみからなり十四種がある。最も活用されているものは、インド原生のワサビノキ(M. oleifera)で、種子から油が採れ、サラダ油、石鹸、油絵の具に使われ、葉や果実は野菜として、根はセイヨウワサビの代用として利用されている。
多肉ユーフォルビアには、通常ミドリサンゴ、またはミルクブッシュと呼ばれる東アフリカ原生のEuphorbia tirucalliがあるが、ここにあるものは小枝が太く、逞しいE. plagiantha。現地のアンタンドロイ族は樹皮を紙の代用として、タバコの巻紙、屋根葺き材としても使っている。
またE. stenocladaは形態がシカツノサンゴ(同属)に似て、人間の肺の末端に至る血管を詰めたような形をして、先端に刺を持つ。一般にトウダイグサ科の樹液は有害だといわれているが、現地ではコブ牛の餌にする。刺の木の林には他にマメ科植物、テイカカズラ属、ミドリノタイコと呼ばれて鉢物にされるウリ科の多肉植物Xerosicyos danguyi、外来のヒモサボテンなどが見られ、そのほか最近エイズに効く成分があるとのことで注目されているニチニチソウも、こんな乾燥地まで生えている。もちろんマダガスカルの原生種だが、湿地や海浜など至る所で見られる雑草で、原種の花色はすべて花の中心が少し濃いピンクである。
ガイドのセルジュの「この辺はサソリが生息している」の話で、急遽サソリ探しとなったが、なかなか見つからない。あきたころに道畔の石をひっくり返すと、体長5から6cmの小さなサソリがでてきた。道に放り出して撮影。次第に弱ってくる。もともとサソリは夜行性で、夜の闇と冷えた空気が大好き、フライパンを熱したような直射日光下の道では10分はもたなかった。
さらに車を進めると、四、五本のバオバブ(Adansonia grandidieri)の大木のわずかな日陰を求める、十五頭のコブ牛がいた。道の際には、荒野の何処から現れたかアンタンドロイ族の子供を含めた一団が何やら露店を広げている。覗いてみると彫刻したグッズで、スプーンやホシガメ、バオバブのミニチュア、実など売っている。材はアルアウディアやディディエレアで、建材、炭などを作るのにも利用されている。彫刻には上手、下手がある。値段は一緒なので必然的に上手な方に客は集まった。延々と続く刺の木の林を見ていると、地球とは思えないような錯覚にとらわれる。オーストラリアの乾燥林、ドリアンドラの林も見てきたが、それとまるきり感覚が異なるのは、広葉植物が極端に少ないせいかもしれない。
○砂漠の中の刑務所
しばらく行くと、忽然とユーカリが繁る集落が現れた。ちょうどトラックの荷台に男達数十人が乗り込み、仕事に出ていくところである。ガイドに聞くと、この集落は刑務所で、受刑者が懲役刑で道路工事に出て行くところだそうだ。塀もなく、広いオープンスペースに木造のコテージが散在し、日除けでユーカリが植えられている。それにしても女、子供の姿もあるではないか?この国ではよほどの重罪入でない限り、家族との暮らしが許されているとのことで、何ともイキというか人間的な計らいではないか。林を割って一本の道が貫いている。遙かかなたの点が次第に近づいてくる。どうやら四輪駆動の車、見る見る近づく。この街道で出会った車らしい初めての自動車。われわれに近づくと停車した。運転者は若い日本人男性である。話を聞くと東京農業大学の学生で湯浅研究室から派遣されて、この乾燥林を研究しているとのことである。
車で出発してから約三時間過ぎたころに刺林が突然切れて、今度はサイザル畑が地平の果てまで続く。これも前述したフランス人のプランテーションである。ベレンティ・ロッジはサイザル畑を抜けた場所にあり、途中二ヶ所にバーをおろしたゲートがあり、チェックを受けてから敷地内に入ることが許される。ゲートからロッジまで数kmあり、私設の飛行場も完備している。ベレンティというから町か大きな集落かと思っていたのは間違いでここの単なる地名らしい。
午前十二時四十分頃到着した。早速にカラカラに渇いた喉に冷えたビールを流し込み昼食をとった。ここは二種類の原猿類、つまりワオキツネザルとベローシファカが多く、われわれの泊るバンガロー周辺にもたくさんいる。ワオキツネザルの雌は子供を背に乗せ、長い黒白のダンダラ紋様のシッポでバランスを取りながら七から十五頭の群で行動している。人間が食べる果物が大好物で人の姿を見ると何かもらえるかと寄ってくる。手から餌を持って行くが、頭を撫でたりすることはできず、人間とは一定の距離を保っているようである。群のリーダーは子持ちの雌のようで、女系中心の家族で構成され、群同士の餌をめぐるテリトリー争いは日常茶飯事で仲が良くない。
ベローシファカは食性の違いからあまり人間に寄りつかず、通常は樹上生活をしている。常食はタマリンド(Tamarindus indica)の若葉や果実である。タマリンドは熱帯アフリカからアジアに分布するマメ科の高木で、東南アジアでは並木などに植えられているが、熱帯地方では食料を得る木として、最も重要なものである。葉や若莢は野菜とされるが、果肉は清涼飲料、ジャム、シャーベット、あるいは酒作りに用いられる。また果肉は、中国では食欲不振や産婦の嘔吐、暑気払いなどの薬として、インドネシアでは調味料、下剤などとして用いられている。ベローシファカはここで撮影されて日本のTVコマーシャルで、「横っ飛びザル」として一躍人気を呼んだが、地上に降りるのは稀で、群が一日に巡回するコースで林や木が途絶えた時、仕方なしに飛び跳ねて次の木を目指す行動なのであって、決して人間を歓迎してダンスを踊っているわけでない。ベレンティの森は日本でいう二級河川のほとりにあり、周囲は乾燥地帯だが、ここだけは地下に湿気があり、広葉樹林が形成されている。川は乾燥のため流れている気配はなく、濁った水溜まりとして、やっと残っているという感じである。
直径7cm位の果実を成らせているイチジク属、ユーカリ属、クスノキ科、マメ科などの混成林がある。林の中でも目立つのは、数百年経たと思われるタマリンドの大木がかなりの密度で自生していることで、猿の餌には事欠かない。古木の洞には夜行性の原猿類イタチキツネザル(sportive lemur)の姿も見られ、人の気配に高さ5、6mの穴からわれわれの行動を見下ろしていたが、昼は視力が弱いとのことで、性能のよい耳だけが働いている様子である。
常緑の広葉樹には、大小のカメレオンを始め頂上部にはチャイロキツネザル(brown lemur)などが生息するなど、かなり生命の賑やかさを感じる。川沿いの森を一周すると乾燥林に出る。
この林は人工林で巨大なバオバブはないが、ワサビノキ属、パキボディウム、ディディエレア科各種、ハナキリン、カランコエ、アロエなど、南部にある固有種がすべて集められている。アロエでは最大のアロエ・ヘレナエ(Aloe helenae)があり、3m以上の高さになる。
パキボディウム・ラメレイ(Pachypodium lamerei)は、実生の幼苗が観賞用に出回っているが、成木になると刺が無くなり、幹は太り、高さ4から5mになる。上部は二股に枝が分岐し、花は白色で、たぶんにキョウチクトウ科の特徴をもち、果実は枝先にバナナ状に2から5本つく。同属でよく似た種にパキボディウム・ジェエイ(P. geayi)がある。園芸名を「亜阿相界」というが、これはアジアとアフリカの界、つまりマダガスカル原生種の意味でつけられたものである。
乾燥した地面は褐色の細砂で、風が吹くと風紋がつき、紋の稜線には黒い砂鉄が残り、褐色とのコントラストが美しい。褐色の土はおそらく酸化鉄やアルミニウムを多く含み、そのまま水に溶かすとベンガラ(弁柄)として赤色顔料に使えそうである。
林の外れにアンタンドロイ族の集落を再現した現地の民家があり、材はすべてディディエレアやアルアウディアで、一戸一戸は小さく、一間×二間位の面積の掘立て小屋である。周囲の生垣もアルアウディアが使われ、中には枝をくねらせて横に張るディディエレア・トローリー(Didierea trollii)が混植されている。この植物は幼木時は地上にのたうつ形で枝を張り、十年以上経つと高さ3、4mに幹が立ち上がり、上部で枝を水平に開張する。全体に刺や葉が細かくびっしりついており、外敵が生垣を突破するのは不可能である。高さ1.2mのコンクリート塀で囲まれている中にマダガスカルホシガメが数十匹飼われている。このカメは陸ガメで、マダガスカル島が大陸だった生証人である。ワシントン条約で国外持出禁止の種で、むろん絶滅危惧種である。南部マダガスカルに生息するがその数は少ない。長さ30から40cmの甲羅の上部に十ヶ所位の少し盛り上がったコブがある。そこを中心として黄色の線条が360度放射されているので、別名ホウシャガメとも呼ばれている。草食性で多肉のアロエ、カランコエなどを食べる。飼うのには、野菜クズが常套手段だが、乾燥地では野菜は高値で、現在は外来種で邪魔物のウチワサボテンも与えるとのことである。かつて無人島であったマダガスカルに人間が渡って来たのが、千五百から二千年前で、原猿類を除けばこれといった哺乳類もなく、長い間サル達の天国だった。
人間の進出とともに、森林の四分の三以上が消滅し、エピオルニスや200kgもある原猿類など、数多くの動植物が絶滅し、現在生き残っているものも絶滅危惧種が多い。残されているものは大変貴重なもので生物の進化、適応性などを学ぶ上でのサンプルがまだまだ揃っている。この貴重な世界の財産が未来永劫存続することを願いつつ島を離れる。
タナナリーボを発ち、二度乗り継いで、成田まで二十時間座り続ける。尻や関節の痛さを差し引いても、貴重な体験であった。
- 初出掲載紙:(社)日本インドア・グリーン協会発行『グリーン・ニュース』
- マダガスカル植生誌No.1(グリーン・ニュース、一九九九年三月号)
- マダガスカル植生誌No.2(グリーン・ニュース、一九九九年五月号)
- マダガスカル植生誌No.3(グリーン・ニュース、一九九九年七月号)
『熱帯植物巡礼』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
書籍詳細
-
完売
[2000/03/25]田中耕次 著 / アボック社 / 2000年 / B6判 286頁
定価1,650円(本体1,500+税)/ ISBN4-900358-51-7
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第20回 『熱帯植物巡礼』
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』